拙者が目覚めたときには、同じ部屋の他の宿泊者3名はもぬけの殻でした。
彼等は散歩に出かけたり、朝食のブレッドの買出しにでかけていました。
女性陣は朝食の準備に余念がありません。
8:00~、皆さんが揃ったところで朝食。
カラフルな野菜サラダ、美味しそうですね!
画像をクリックすると大画面でご覧になれます
午前中、車に分乗してK.T-sanが軽井沢の観光名所、白糸の滝と見晴台へ案内してください
ました。
先ず、白糸の滝です。
旧軽銀座から三笠通りに入り、白糸ハイランドウェイ(有料)料金所から約8km、約10分走り、
白糸の滝バス停へ。
ここから、なだらかな山道を歩いて10分程、突き当りに白糸の滝です。
拙者、ここは2回目の訪問でしたので記憶があります。
この時季、ご覧の通り冬枯れの滝でした。
外国人ツーリストも多かったのは驚きでした。
|
|
|
|
|
| 白糸の滝 (2023.12.17_10:43) |
白糸の滝からの流れ出た水は湯川の源流です
(2023.12.17_10:44) |
高さ3m、幅70mの湾曲した岩肌より数百条の地下水が落下する滝です。
滝の水は湯川となり千曲川に合流するようです。
T.K-sanは、白糸の滝といえば彼の地元近くの富士宮市にあるものだけと思っていたようです。
全国津々浦々にありますよ。
勿論、富士宮市の白糸の滝は世界遺産でもあり、規模としてはおそらく日本一でしょう。
この後、旧軽銀座から約4Kmの長野県と群馬県の県境に近いという見晴台近くの神社、熊野
皇大神社へ。
ここは中山道の旧碓氷峠の頂上、標高1200mに位置しているそうです。
拙者、過去にこの神社前を何回か通過したことがあります。
勿論、AIOIクラブのイベントのサイクリングやハイキングの時でした。
記録にも残っていますがずいぶん昔ですネ!
Diary-196/2009.10.13 と Diary-383/2011.08.19
そんなことで、周りの風景は記憶にありましたが、この神社を拝観するのは初めてです。
|
|
| 熊野皇大神宮の拝観のために石段を上る面々 (2023.12.17_Photo by T.S-san) |
参道と本宮の中央を県境が通っていて社殿が両県にまたがっている珍しい神社なんです。
県境を挟んで二つの神社が並立していて、向かって参道の石段より左側が長野県側の熊野皇大
神宮、右側が群馬県側の熊野神社というそうです。
画像をクリックすると大画面でご覧になれます
|
|
熊野皇大神宮の隋身門 ↑
← 隋身門の直下の参道に刻まれた県境の
標識 (2023.12.17_11:18)
|
|
|
本宮を参拝。
今年の無病息災に感謝し、今後のファミリーの健康を祈願しました。
|
|
| 本宮に参拝する面々 (2023.12.17_11:19) |
境内にはパワースポットとしてのご神木がありました。
推定樹齢850年のシナノキです。
説明によると、長野県にはシナノキが多く分布していて、「信濃」の由来になったのだそうです。
なるほどと思わせる言い伝えですね。
画像をクリツクすると大画面でご覧になれます
|
|
|
|
| シナノキ (2023.12.17_11:23) (Photo by Sugihiro) |
熊野皇大神宮のシナノキの
説明 |
神社前の峠の風景です。
駐車場の看板やその他にヤタガラス(八咫烏)のイラストを見かけました。
なんでも八咫烏は熊野皇大神宮の神使だそうで、それで納得しました。
 |
| 神社前の峠の風景 (2023.12.17_11:34) |
|
 |
| 駐車場の看板に八咫烏のイラスト(2023.12.17_11:33) |
|
 |
| 八咫烏のイラストの一つ |
|
神話によると、日本武尊(ヤマトタケル)が東征の帰路、碓氷峠に差しかかった折に濃霧で道に
迷った。 その時、一羽のヤタガラスが現れ先導し無事に頂上に案内したとのこと。
拙者、プロ野球やプロサッカーの観戦が趣味の一つです。
そのサッカーの日本代表や日本サッカー協会のエンブレムの意匠に使われているので馴染みが
あります。
このHPでも過去に、「2018・FIFA World Cup出場国のエンブレム」としてDiary-867で取り
上げています。 お暇ならご覧になってください。
これで今日のスケジュールは終了し下山。
他の皆さんは、グループ毎に寄り道をしながら帰途に着きました。
ちょうど昼時でしたので、残っていたK.K-sanさんとともにK.T-sanからラーメン屋での昼食を
誘われました。
別荘から歩いてめっちゃ細い道を進むと、程近い途中に中華そば「美乃屋」がありました。
昔ながらのラーメン店風で、おばちゃんが一人で切り盛りしていました。
驚いたことに、こんなところにと言うと失礼ですが、外国人ツーリストと思しき二組のお客が入って
いたのです。
きっと、お店の口コミランキングが★★★★★だったのでしょう。
拙者が食べたもやし味噌ラーメン、たしかに美味しかったので納得しました。
スマホの威力は世界レベルで凄いですネ!
久し振りの忘年会で昔のヨット仲間にお会いできてとても楽しいひと時でした。
来シーズンには、岡山・牛窓ヨットハーバーからカタマランでの瀬戸内海クルーズを楽しみにして
います。
それでは皆さん 良いお年をお迎えください。
久し振りにヨットクラブAIOIの忘年会に参加しました。
昨年は娘一家の一時帰国があり、そのお世話で都合がつかず欠席したため、2021年の伊東
での忘年会(Diary-2.1060)以来、2年振りです。
今年、AIOI号に乗船したのは3月の伊東⇄初島セーリング(Diary-2.1117)が最初にして
最後でした。
その後、AIOI号のオーナーK.T-sanがリタイア後のヨットライフをエンジョイするため、これまで
のAIOIⅥ号を譲渡され、新艇、双胴型AIOIⅦ号を購入。
岡山の牛窓ヨットハーバーを母港に瀬戸内海でデビューを果たされました。
瀬戸内海クルーズにお誘いがあったものの拙者の都合がつかず未だお目にかかっていません。
AIOIクルーメンバーともご無沙汰していました。
|
|
| 牛窓ヨットハーバー(岡山県)のロケーション |
AIOIⅦ号(Notion/『AIOI 7について』から転載) |
そんな折、忘年会のお誘いがあり、久し振りにAIOIの皆さんとお会いしたくて参加してきま
した。
今回の会場は軽井沢にあるK.T-sanの別荘です。
ここを訪れるのも2020千曲川サイクリング(Diary-2.1003)以来3年ぶりです。
8:00に草津の自宅を出て、二つの新幹線を利用し京都➡東京➡軽井沢のルートで軽井沢駅
13:20でした。
K.T-sanの車で13:30、別荘着。 お迎えありがとうございました。
積雪で寒い軽井沢を想定していましたが、この日の軽井沢はどうしたことか小春日和 の の
暖かさで忘年会日和( )でした。 )でした。
既に数名が車や列車で到着済みで、15:00までに全員がトウチャコ。
皆さんお変わりなくお元気なようでなによりでした。
参加者は11名+ワンちゃん×2です。
大先輩のT.K-sanも御殿場から仲間と共に参加しい下さいました。
うれしかったです。
皆さんで協力して2部屋の空きスペースに男性用雑魚寝の寝床を準備。
夜の準備もできたところで、2台の車で忘年会の前座である温泉・トンボの湯へ湯浴みに。
途中、軽井沢高原教会でキャンドルイベントが行われているとのことで案内してもらいました。
ちようど、夕闇迫る頃でしたので、教会の森一面には数多くのランタンが灯され一足早いクリス
マス気分を味わさせていただきました。
|
|
| 軽井沢高原教会前の森に広がるランタンキャンドル (2023.12.16_16:30) |
お馴染みの星野温泉 トンボの湯です。
周りにのツリーにはイルミネーシヨンが灯り湯浴み客を引き付けていました。
|
|
|
| 灯りの灯った星野温泉 トンボの湯 (2023.12.16_17:43) |
小一時間ほど露天温泉でゆったりと温泉を楽しみました。
この後、忘年会の会場、スペイン料理・グラナダ軽井沢へ。
ここは、AIOIのメンバー御用達のお馴染みのお店です。
18:00~、二つのテーブルに分かれて、先ずはスペインビールで乾杯して宴会スタート。
料理は注文してから20~30分はかかるので、前菜としてスペイン生ハム・ハモンセラーノで。
|
|
|
| スペインビールで乾杯 (2023.12.16_18:16) |
スペイン生ハム・ハモンセラーノ (2023.12.16_18:20) |
お後はスペイン RIOJA赤ワイン。
ビールの後はスペイン・赤ワイン ↑
最初はRIOJA赤ワイン →
(2023.12.16_18:36) |
|
ワインとともに口舌も滑らかになったところで、AIOI 7での瀬戸内海でのヨットライフやら
その他の四方山話に花が咲きました。
|
|
|
| シーフードパエリアも登場して宴たけなわ (2023.12.16_19:31) |
|
|
料理も続々と出てきました。
アサリ/エビのアヒージョ、トルティージャ(スペイン風オムレツ)、キャベツとアンチョビのサラダ、
ほうれん草とベーコンのサラダ。
|
|
|
|
| トルティージャ |
エビのアヒージョ |
キャベツとアンチョビのサラダ他 |
最後は白ワインでイカ墨パエリア。
白ワインはビエンベビード プルポ(BIENBEBIDO PULPO)。
おもろいことにラベルはタコの絵柄ですよ。
ラベルには、COME PULPO y BEBE VINOとあります。
スマホで調べてみると、意味は「タコを食べてワインを飲む」とのこと。
どなたがオーダーしたのかイカ墨のパエリアに合わせてくれたのでしょう。(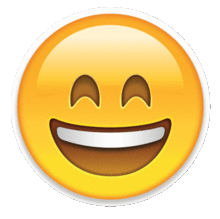 ) )
いやあ、美味しかった!!!
|
|
|
| イカ墨パエリア (2023.12.16_20:04) |
スペインワイン BIENBEBIDO PULPO
(2023.12.16_20:22) |
二次会はK.T-san別荘に戻りスーパークーリングワインやウイスキーで。
|
|
| 二次会はスーパークーリングワインで乾杯 (2023.12.16_) |
 |
 |
|
こうして、若い皆さんとの楽しい忘年会は自然散会となり、思い思いに床に着きました。
続く Diary-2.1146 / 「2023・AIOI忘年会@軽井沢(2/2-12月17日)」 Diary-2.1146 / 「2023・AIOI忘年会@軽井沢(2/2-12月17日)」
いこい会関東地区の忘年会に参加してきました。
今年最初の早い忘年会です。
東京ではビジネスマンの忘年会が師走の中旬以降に集中しているから、この時期になったので
しょう。
いこい会を構成する同窓生が所属した学科は全50名で、その内の32%、16名が関東地区の
企業や研究所への就職等でこの地域に定住しています。
しかし、傘寿の歳ともなると体のあちこちの老化現象で不具合が現れるからでしょうか、忘年会
出席者は年々減少し、参加者は関東在住者の約半分、9名になりました。
今回、久し振りに八王子からY.K-sanも参加してくれました。
今年の集まりは1月の新年会、10月の暑気払い(今年は酷暑のためこの月まで延期された)に
続いて3回目です。 いずれも御徒町駅前にある吉池食堂で開催。
今回はメンバーのN.W-sanの紹介で会場は千代田区内幸町の日比谷中日ビル内にある会員
制レストラン、シーボニアメンズクラブで12:00開宴です。
我々の場合、歳も歳ですので最近では忘年会といってもお昼開催に設定されています。
新橋駅から地下鉄銀座線で虎ノ門駅下車徒歩6分。
Google Mapsの経路ナビに誘導してもらい街の景色を眺めながら会場へ。
会場は国会通りに面していて、通りの向こう側が日比谷公園でした。
いやあ、さすが日本の首都、東京は街か゛美しいですね!
|
|
| 日比谷中日ビル前から国会通りを望む (2023.12.01_11:44) |
会場入口で先着の皆さんが待ってくれていました。
|
|
| 日比谷中日ビル内のレストラン・シーボニアメンズクラブの入口 (2023.12.01_11:55) |
ランチバイキングとのことでしたが、個室ダイニングでした。
レストラン・スタッフによると、コロナ禍により当局の要請でバイキングから様式が変更され個室
ダイニングに変わったとのことでした。
ランチバイキングに替わるメニューとして赤ワイン(飲み放題)付きの「洋食日替わりランチセット」
でした。
テーブルには、赤ワインのデキャンタが三つ置かれていました。
生ビールで乾杯し、お後は赤ワインで昼食をとりながらいつものように賑やかな会話が続き
ました。
日常生活、趣味、持病の他、なんといっても終活の話題が多かったですね。
メニューは、前菜サラダ/スープ/パン/メインディッシュ(魚料理
or肉料理の二択)/デザート/コーヒーです。
会話がはずみ写真を撮るのをすっかり忘れていました。
ピンチヒッターとしてレストランのHPにぴったりした料理セットが
載っていたので転載しておきます。
話の途中、総幹事長のT.K-sanからびっくりした話がありました。
最近、脚に変調をきたし神経内科で精密検査を受けたところパーキンソン病と宣告されたとの
ことです。
拙者の弟も50代で発症したので、参考までに事例をお話しておきました。
この病、徐々にではあるが運動機能の障害が出てくるのを見ています。
幸い彼の場合、この歳になってからの発症ですので病の進行は遅いでしょう。
運動機能のリハビリを続ければ、余命は全うできるでしょう。
次の会合は新年会です。
久し振りに住重赤坂寮での再開のリクエストが多くあり、T.N-sanに予約のお願いをしました。
2時間の会合もお開きになり、皆さんと記念写真に収まりました。
この会場、なかなか感じが良く、とてもリーズナブルでしたね。
|
|
| 恒例の全員での記念写真 (2023.12.01_14:02) |
午後の国会通りの写真を二つ。
|
|
|
| 国会通りの向こうの日比谷公園を望む |
国会通りを望む |
二次会は地下の喫茶店ピノキオで。
軽くコーヒーを一杯飲んで散会しました。
|
|
| 喫茶店ピノキオで二次会 (2023.12.01_14:08) |
忘年会が終わるとクリスマス、そして新しい年がやってきます。
あっという間の1年が過ぎ、また一つ歳を重ねます。
歳を重ねると何が起こるかわかりませんね。
傘寿まで生かされていることに感謝し、お互いに元気なうちにいっぱい遊んでおきましょう。
それでは皆さん、また新年会でお会いしましょう
良いお年をお迎えください。
圓光寺を出て最後の紅葉狩りの地、曼殊院門跡に向かいます。
圓光寺前の道路を北に向かい、案内標識に従って曼殊院道まで歩き、ここで右折して東へ直進
すると曼殊院参道入口に。
圓光寺から約1Km、歩いて約15分の距離です。
参道入口にある石碑の周囲の紅葉が色鮮やかに染まっていました。
|
|
| 曼殊院参道入口付近の鮮やかな紅葉 (2023.11.25_11:55) |
ここから紅葉のトンネルのなだらかな坂道を上がっていきます。
紅葉のグラデーションがなんとも美しいですね---。
|
|
| 参道の紅葉のトンネル (2023.11.25_11:57) |
参道の途中、左手の脇道に逸れると鳥居が立ち、正面に弁天堂があります。
この周りの紅葉は真っ赤に染まっていました。
|
|
| 弁天堂境内の真っ赤に染まった紅葉 (2023.11.25_11:58) |
参道を登りきると正面に曼殊院門跡の正門である勅使門が。
曼殊院門跡の「門跡」とは、皇族や貴族の子弟が代々住職を務める別格寺院を指します。
|
|
| 曼殊院門跡の勅使門と紅葉 (2023.12.25_11:59) |
勅使門の白い築地塀に沿って紅葉を楽しみながら北通用門へ向かいます。
白壁に映える紅葉の朱色と斜面の苔の緑のコントラストが際立ち鮮やかでした。
いや、ホントに、曼殊院では、境内で紅葉を拝観するまでの途中で紅葉を満喫できるのが一つの
特徴ですネ!
そんなことを感じました。
画像をクリックすると大画面でご覧になれます
|
|
|
| 白い築地塀に映える紅葉と緑の苔のコントラスト 82023.12.25_12:01) |
右折して石畳の坂を上がると、拝観者が出入りする北通用門があり
ました。 受付で拝観料600円と引き換えに「曼殊院門跡」のリーフレット
を貰い内部へ。
|
|
|
北通用門へ通じる石畳の坂道と紅葉
(2023.11.25_12:02) |
拝観入口である北通用門 (2023.11.25_12:03) |
ここで、曼殊院門跡についてご紹介しておきます。
天台宗の寺院。 山号はなし。 本尊は阿弥陀如来坐像。
開山は是算(ぜさん)。 創建年は天暦年間(947年-9571年)。
竹内門跡とも呼ばれる門跡寺院であり、青連院、三千院(梶井門跡)、妙法院、毘沙門堂
門跡と並び、天台五門跡の1つに数えられる。
最澄(767年-822年)の時代に比叡山上に草創された坊(小寺院)が起源とされる。
その後、北山(現・京都市右京区・鹿苑寺付近)や洛中(現・京都市右京区・相国寺付近)への
移転を経て、1656年(明暦2年)に桂離宮の創始者、八条宮智仁親王の第二皇子良尚法
親王により現在の地に移された。
寺伝では延暦年間(782年-806年)、最澄が鎮護国家の道場として比叡山に創建した
のがその起源とされる。 (鎮護国家とは、仏教には国家を守護・安定させる力があるとす
る思想。)
その後、天暦年間(947年-957年)是算国師の時、比叡山三塔のうちの西塔北谷に移り、
東尾坊と称したという。 曼殊院ではこの是算を初代としている。
曼殊院は平安時代以来、近世末期に至るまで北野神社(現・北野天満宮)と関係が深か
った。 是算が菅原氏の出身であったことから、菅原道真を祭神とする北野神社の初代別当
になったという。 以後、明治維新まで900年間曼殊院は北野別当職を歴任した。
詳しくは、下記資料をクリックしてご覧ください。
(1)曼殊院門跡-オフィシャルサイト- (manshuinmonzeki.jp)
(2)曼殊院(京都市左京区) - Wikipedia
|
曼殊院門跡の境内はこのようになっています。
受付のすぐ前にある庫裏(重文)玄関から拝観が始まります。
庫裏とは寺院の台所に相当するお堂のことです。
入口の大妻屋根には良尚親王筆の「媚竈」の扁額が掲げられたいました。
論語八佾編にある「その奥に媚びんよりは、むしろ竈に媚びよ」を引用したもの。
奥にいる権力者に媚びるのではなく、竈でせっせと働く者、実力者を大切にせよ という意味とか。
(注)論語とは、孔子が弟子と問答した内容を孔子の死後に弟子が書物(20編512文)として残したもの。
八佾編では、器の大きい人の考え方を説いています。
|
|
| 庫裏玄関の大妻屋根にある扁額「媚竈」 (2023.11.25_12:10) |
庫裏から大玄関へと進むと、「虎の間」、「竹の間」、「孔雀の間」があり、その名前の通り各部屋の
襖には「虎」、「竹」、「孔雀」が描かれています。
虎の間の襖絵(重文)は狩野永徳の筆である。
残念ながら、曼殊院では建物内は庭園を除いて写真撮影禁止となっています。
ということで、上記のような所蔵宝物は曼殊院のホームページ/所蔵宝物でご覧下さい。
尚、曼殊院には国宝に指定された宝物があります。
絹本著色不動明王像(黄不動)と古今和歌集(曼殊院本)ですが、いずれも京都国立博物館に寄託されています。
それぞれの画像は、黄不動 - Wikipediaと曼殊院本古今和歌集 - Wikipediaでご覧ください。
大玄関から渡り廊下を進むと大書院(重文)です。
大書院は1656年(明暦2年)の建立。 数寄屋風書院の代表的な遺構とされています。
「仏間」、「滝の間」、「十雪の間」などがあります。
「滝の間」、「十雪の間」では狩野探幽筆の襖絵が見られます。
違い棚は桂離宮のものと同じ造りで、同じ時期に造られたものだそうです。
ちなみに、大書院が曼殊院の本堂に相当するそうです。
その奥に小書院(重文)がありました。
大書院とともに書院建築の代表的なものといわれています。
「富士の間」と「黄昏の間」があり、いずれの襖も狩野探幽筆。
大書院と小書院の南側に枯山水庭園(名勝)が広がっています。
不老不死を求める神仙蓬莱思想に基づいた枯山水庭園。
枯山水庭園を彩る紅葉は今が見頃でした。
拝観者の皆さんは赤い毛氈の敷かれた濡れ縁に座って紅葉に浸っている姿がありました。
その景色を幾つか。
小書院から眺めた額縁庭園です。
|
|
| 小書院から眺めた枯山水を彩る紅葉の額縁庭園 (2023.11.25_12:19) |
ズームアップしたのが下の写真です
リーフレットの解説によると、庭の芯に滝石があり、白砂の水が流れ出て、滝の前の水分石から
ひろがり、鶴島と亀島とがある。
まさにその景色ですね。 白砂が大海を表しています。
|
|
| 滝石(中央奥)から流れ出た白砂の水が水分石からひろがる様子/右手前が亀島 (2023.11.25_12:20) |
亀島には苔地にサツキと松、鶴島には五葉の松(樹齢約400年)があって鶴をかたどって
います。
鶴島の松の根元には、かすかにキリシタン燈籠(クルス燈籠又は曼殊院燈籠と呼ばれる)が
見えます。
|
|
|
| 亀島(手前中央)と紅葉 (2023.11.25_12:20) |
大書院から眺めた鶴島の五葉の松(中央)と紅葉
(2023.11.25_12:22) |
大書院から渡り廊下を通って宸殿の方に向かいます。
リーフレットの説明によると、この宸殿は昨年、明暦年間に建立された旧宸殿を復興再建された
ものです。
旧宸殿は明治5年に京都療病院(現、府立病院)新設のため明治新政府に上納され競売にかけ
られ売却されたが、現宸殿は150年ぶりの復元とのことです。
これまで大書院にお祀りされていた本尊の阿弥陀如来像や北野天満宮から移された十一面観音
などが宸殿に移され、本堂として使用されている。
宸殿の前には新しく作庭された大きな枯山水の庭園、盲亀浮木の庭が広がっています。
大海に住む目の見えない亀が、百年に一度海中から頭を出した。 そこへ風に吹かれるまま流さ
れてきた節穴のある流木が流れてきて、亀の頭が偶然にもその節穴にはまるという、極めて低い
確率の偶然性を表すたとえ話である。
人間に生まれること、仏教に出会う難しさを表す。
左の流木に見立てた石は天然記念物の貴船岩だそうです。
|
|
|
| 盲亀浮木の庭を望む (2023.11.25_12:23) |
宸殿から別の角度で眺めた紅葉です。
何度見ても美しいですね。
|
|
| 宸殿から眺めた庭の紅葉 (2023.11.25_12:23) |
これで曼殊院での紅葉狩りを終え帰途に就きます。
帰路、名残を惜しみながら再び紅葉をパチリパチリ。
曼殊院から歩いて白川通に出て、一乗寺清水町(バス停)から京都市バスで京都駅へ。
京都駅前地下街ポルタにある「お好み焼きここやねん」に入り遅い昼食。
紅葉狩りの余韻に浸りながら鉄板焼きで一杯、至福のひと時でした。
詩仙堂を出て圓光寺に向かいます。
詩仙堂前の坂道を20mほど下り、右折して生活道路を約150mほど歩くと3分程で圓光寺が
右手に。
山門前には拝観予約者の列ができていました。
秋の紅葉特別拝観(11/11~12/5)は混雑を避けるために予約制となっているからです。
拙者の拝観予約時間は11:00からです。
少し早く着きましたので、待ち時間に記念写真。
|
|
|
| 圓光寺の由緒 (2023.11.25_10:25) |
山門前の拝観者の列 (2023.11.25_10:36) |
|
|
| 山門前で記念写真 (2023.11.25_10:37) |
ここで、圓光寺についてご紹介しておきます。
臨済宗南禅寺派の寺院。 山号は瑞巌山(ずいがんさん)。 本尊は千手観世音菩薩
坐像(伝・運慶作)。
開基は徳川家康。 創建年は1601年(慶長6年)。
徳川家康が1601年(慶長6年)に国内教学の発展を図るため、足利学校の第九代学頭・
三要元佶(閑室)禅師を招き、伏見城下に圓光寺を建立し学校としました。
圓光寺学校が開かれると、僧俗を問わず入学が許されました。
また、『孔子家語』、『貞観政要』など多くの儒学・兵法関連の書物が刊行されました。
これらの書物は伏見版または圓光寺版と呼ばれ、そのときに使用された木製の活字が
保存されていて、その数は約5万個にのぼり日本最古の活字として重要文化財に指定
されています。
その後、当寺は相国寺内に移り、更に三世・澤雲租兌禅師のとき、1677年(寛文7年)に
現在地に移された。
明治時代以降、臨済宗南禅寺派の尼僧の修行道場となっていた時もあった。
詳しくは、下記資料をクリックしてご覧ください。
(1)瑞巌山 圓光寺|Zuiganzan Enkouji Temple
(2)円光寺 (京都市左京区) - Wikipedia
|
定刻近くになり予約チケットのチェックがあり、山門をくぐって受付で拝観手続き完了(拝観料
1000円、通常拝観時は600円)。
圓光寺の境内はこのようになっています。
画像をクリックすると大画面でご覧になれます
石畳の参道を進むと眼前に枯山水の庭園「奔龍庭」がダイナミックに広がっています。
渦を巻いた様々な流れを見せる白砂は雲海を、石組みが自在に奔る龍をあらわしているそう
です。
画像をクリックすると大画面でご覧になれます
|
|
| 瑞雲閣(正面)の前に広がる枯山水の庭園「奔龍庭」 (2023.11.25_10:55) |
|
|
|
| 龍が奔り雲海が煌めく奔龍庭 (2023.11.25_10:55) |
参道を挟んで瑞雲閣の正面には唐破風の屋根がある本堂の玄関口があり、煌びやかな
襖絵が迎えてくれます。
渡辺章雄作 「琳派彩還 四季草花図」とあります。
四季草花図には、勿論紅葉も描かれていました。
(注1)琳派とは、日本美術の特色である装飾性を最も純粋かつ高度に表現した流派とされる。
背景に金銀箔を用いたり、大胆な構図、型紙のパターンを用いた繰り返し、たらしこみ技法などに特色が見ら
れる。 題材は花木・草花が多いが、物語絵を中心とする人物画や鳥獣、山水、風月に若干の仏画を扱った
作品もある。
(注2)渡辺章雄 ; 「創画会」で活動する日本画家
|
|
|
| 本堂の玄関 (2023.11.25_10:56) |
渡辺章雄作 「琳派彩還 四季草花図」 |
扁額に「十牛之庭」とある中門をくぐると、燃えるような紅葉が目に飛び込んできます。
|
|
|
| 奔龍庭より中門を望む (2023.11.25_10:57) |
十牛之庭の紅葉 (2023.11.25_10:57) |
本堂の別の玄関口に水琴窟がありました。
水琴窟は地中の空洞に水滴の音を響かせ、その音を楽しむというものです。
縁が広い盃型の手水鉢を用いた水琴窟はあまり例がなく、古くから「圓光寺型」として多くの
趣味人に愛されてきたとか。
一滴一滴が奏でる澄んだ音色は拝観者に心地良い余韻を残し、心を癒し和ませてくれます。
いやあ、風情がありますね!
|
|
|
| 圓光寺型の水琴窟 (2023.11.25_10:58) |
本堂に入り書院へ進むと、身動きのとれないくらいに多くの参拝客が畳に座り、スマホやカメラ
を十牛之庭に向けています。
縁側には赤い毛氈が敷かれていて雅やかな趣があります。
隙間ができたところで拙者も座り込み、色鮮やかで名作絵画のような額縁庭園を眺め、シャッター
ボタンを押しました。
赤や黄色に色付いたもみじ、見事でした。
|
|
|
|
|
| 本堂からの額縁庭園(十牛の庭)の眺め (2023.11.25_11:03~11:07) |
十牛之庭とは変わった名前ですね。
圓光寺パンフによると、牛を追う牧童の様子が描かれた「十牛図」を題材にして、江戸時代に造ら
れた池泉回遊式庭園です。
十牛図に描かれた牛は、人間が生まれながらに持っている仏心をあらわしています。
牧童が禅の悟りにいたるまでの道程であり、懸命に探し求めていた悟りは自らの中にあったとい
う物語だそうです。
外に出て十牛之庭を散策しながら紅葉を楽しみました。
苔庭の散り落ち葉も趣がありますね。
瑞雲閣に入り、寺宝の展示を見学しました。
日本最古の木製活字です。
|
|
|
| 伏見版木活字(圓光寺版) (重文) (2023.11.25_11:16) |
円山応挙が寺内の竹林を描いた「雨竹風竹図」です。
よく見ると、一滴の雨も一筋の風も描かれていないのですが、風に舞う竹のしなりや雨に煙る
竹を抒情的に墨で描いた作品と言われています。
|
|
|
| 紙本墨画「雨竹風竹図」 六曲屏風一双 (円山応挙筆 重文) |
江戸時代中期の絵師、渡部始興筆の「松下寿老人図」です。
その他、ここに展示されていない寺宝である「開山元桔禅師像」と「本尊 千手観音菩薩坐像」も
圓光寺HPから転載しておきます。
|
|
|
|
松下寿老人図
(渡部始興 筆) |
開山元桔禅師像 (重文) |
本尊 千手観音菩薩坐像 (伝運慶作) |
瑞雲閣の内部へ進むと、ここでも多くの皆さんが縁側に座って今が見頃の紅葉を息をのんで
見入っているようでした。
本堂の書院とはまた違う角度から十牛の庭を楽しめますね。
玄関先にある上部が火炎形の花頭窓からも見事な紅葉を覗きみられます。
|
|
|
|
|
| 花頭窓と花頭窓から眺めた紅葉の景色 (2023.11.25_11:22) |
庭園に出て東照宮や徳川家康の墓(家康の歯が埋葬されているとか。)があるという裏山の
高台の方へ登ってみることにしました。
家康ゆかりの地であるからでしょうか?
途中の庭園で、あまりに綺麗なので再び紅葉の写真をパチリ、パチリ。
赤から黄色、緑色へとグラデーションがなんとも鮮やかです。
坂道を登っていくと鐘楼が。
|
|
| 紅葉に囲まれた鐘楼 (2023.11.25_11:26) |
裏山の階段を上っていくと高台があり、ヒノキが高く聳える杜のなかに東照宮などがあります。
ビュウスポットに移ると、眼下には真っ赤な紅葉に囲まれた圓光寺の境内と彼方の洛北の街が。
素晴らしい眺めでした。
海外からの観光客のお姉さまが拙者の写真を撮ってくれはりました。
ありがとう。

高台の展望スポットからの眺め ↑
眼下の紅葉を背景に記念写真 →
(2023.11.25_11:34)
|
|
|
引き返し、孟宗竹の竹林のある道を下りていきます。
竹の節の輪が一本しかないのでそれと分かりますね。
瑞雲閣に展示されていた円山応挙筆の「雨竹風竹図」に描かれていた竹林かもしれませんね。
応挙竹林と呼ぶそうですからきっとそうでしょう。
竹林と紅葉のコラボレーションも素晴らしいですね!
画像をクリックすると大画面でご覧になれます
|
|
|
| 孟宗竹林と紅葉のコラボレーション (2023.11.25_11:39) |
十牛之庭にある洛北最古の泉水と言われる「栖龍池」がありました。
グラデーションのある紅葉が覆いかぶさるように垂れ下がり、水面に映し出されています。
なかなか風情のある景色ですね。
|
|
|
|
|
| 栖龍池に覆いかぶさる紅葉と水面に映る反射像 (2023.11.25_11:40) |
いやあ、素晴らしい紅葉を見せてもらいました。
そんな圓光寺に名残を惜しみながら、本日最後の紅葉狩りの地、曼殊院に向かいました。
続く diary-2.1143 / 「2023紅葉狩り@京都(3/3-曼殊院)」 diary-2.1143 / 「2023紅葉狩り@京都(3/3-曼殊院)」
 TOPページへ戻る TOPページへ戻る
|
|