Diary/Archive
�@�@�@�@�@�@2023�N03�� |
�@���ւ̐����������邽�߁A�n��̈�ÃZ���^�[�ł���W�C��ÃZ���^�[�ցB
�쑐�Âɂ��邱�̕a�@�ւ͋߂��̃o�X�₩���20���B
��t�J�n����(8:30)�ɊO����t�Ŏ����������ď�������Ȃ̎�f��\���A���������
�ڍׂȖ�f���S����̐f�Â��܂����B
�@�S����ɂ͌��֑O��̏�ߋ��̈ݒ��̌��f�A���a�̗L���Ȃǐ����B
�ʒk�r���A�َ҂���傩��G�f���A�m���ɏo���̍��Ղ����邱�Ƃ��m�F����܂����B
�a�@��PC�ɕۑ�����Ă������N��CT�����̎ʐ^�ɂ͌e��������Ƃ̂��Ƃł��B
���ւ̌�����������Ȃ��̂Ő悸�咰���������������āA���̌��ʂ����܂��傤�ƁB
�������ʂɂ���Ă͑����@�Ƃ��ʍ�����܂����B
�@�َҁA�e���Ƃ������t�͏����ł��B
��t�ɐq�˂�ƁA������(���ɑ咰�ɑ���)�̈ꕔ���O���ɓ˂��o����ɂȂ�����Ԃ̂���
(�������猩��Ə����ǂ̕ǂɂł����̂��ڂ�)�ł����A�e�����͕̂a�C�ł͂Ȃ��Ƃ̂���
�ł��B
���ۂ�Net�Œ��ׂĂ݂�Ƃ���ȏ�Ԃ̂��Ƃ������悤�ł��B
�@�����̗���́A�̌��˓_�H�ˑ咰�����������B
���́A�_�H����̂�������܂���B
���̌��ǂɓ_�H���u��t���ĕ����̂����܂�ď��߂Ăł��B
�@�_�H���u��t�����܂ܓ������������֍s���ƁA�����̑O�������ƌ����ĉ��܂����܂���
�܂����B
�j�t���b�N�z�����p�܂Ƃ������܂ł��B
�咰�����A�r�ւ𑣐i���A����(�E���R)�����S�ɏ������邽�߂̂���ŁA�������ɂ��
�������X���[�X�ɂł���悤�ɂ��邽�߂Ƃ̂��Ƃł��B
15��/10���Ԋu�ŃR�b�v2�t�̉��܂����݁A�����r�ւ��J��Ԃ��A2���Ԃ����ĉ���2���b�g����
���݊��������ɂ͕��ւ͂قڔr������Ă���悤�ł��B
|
|
|
���܂̃j�t���b�N�z�����p��(2L)
(2023.03.31_12.15) |
�j�t���b�N�̓������@�Ɠ����o�߂̃`�F�b�N(2023.03.31_12.15)
|
�@�O�������I���ƁA�����������鏊�Ɍ����������p���c���͂��܂��B
����!�@�����������ł��B
���Í܂��_�H���ɓ�����A�Q��ɉ������ɂȂ�܂��B
���ɏ����p�[���[���h���A���������咰�֓����Ă����̂�������܂��B
�������}���ɂ��ɂ݂��a��������Ȃɖ��������ł��l!
�@�咰�������̎d�g�݂́A�T���ȉ��̒ʂ�ł��B
���A�咰�r�f�I�X�R�[�v�̑����͖�12mm�A������150cm�������ł��B
�@�����S����ɂ��ƁA�������͑咰�̈�ԉ��ɂ���Ӓ��܂ő}�����ꂽ��A�����������X��
�����Ȃ���咰�̊ώ@���s���Ƃ̂��Ƃł��B
�����������C�����Ē����L���A�����Ɏc���Ă���A�≘���K�X���Ő�Ȃ���A����
�̌��������Ȃ��悤�Ɋώ@����܂��B
�@�������̑咰���̉f�������A���^�C���Ń��j�^�[��Ō����Ă��������܂����B
�����̉�����������̓r�j�[���p�C�v����r�o����Ă��܂����A�����������Ă���̂�
���ĂƂ�܂����B
�@�َ҂̑咰�ɂ͊���̌e���������A�Ȃ��Ȃ��o������T���̂ɋ�J����Ă��܂����B
�o���̂���2�ӏ��̌e���ɑ��āA����������̑���ɂ��z�b�`�L�X�Ŏ~�����Ă�������
�܂����B
��20���������Č����͏I���B
���A�؏�����قǂ̑傫���̃|���[�v�͖����Ƃ̂��Ƃň��S���܂����B
�@��w�̐i���͂������ł��l!
���N�A������f�ő咰�������Ă��܂������A����́u���������v�ɂ����̂ł����B
����͑咰�������ɂ�鐸�������ɐ�ւ��悤�Ƃ̎v���ɂ�����܂����B
�@������ĂсA�S����Ɠ������ʐ^�����Ȃ���ʒk���A���ւ̏Ǐ�͑咰�e���o��(�a��)��
�����̂Ɛf�f����A�������@�ƂȂ���@���Ԃ͖�5���ƂȂ�܂����B
�@���@�葱�������āA���@�f�Ìv�揑�ȂNJ���̓��ӏ��◘�p�\�����ɃT�C���B
���炭����ƁA�a������Ō�t����̎Ԉ֎q�ɂ�邨�}�����B
�_�H���u��t���Ȃ���I�b�`���A�I�b�`���ƕa���������܂����B
�@�_���a���͌�(��)�Ɉē�������@�������X�^�[�g�B
���z�����͑S�z���ȕ��S��6,600�~/��(�ō�)�B
���̃X�y�[�X�́A���傤�ǃr�W�l�X�z�e�����x�̍L���ł����B
���җp�Q��A���ʑ�A�V�����[�ATV�A�①�� etc�̐ݔ�������ATV�Ɨ①�ɂ̎g�p�ɂ̓v���y�C
�h�J�[�h���K�v�Ƃ̂��Ƃł��B
|
|
| �َ҂̕a��(�W�C��ÃZ���^�[)�@(2023.03.31_23:57) |
�@���炭���āA�S���Ō�t����_�Ă����������^���̓��@�K���i�����܂����B
�a���p�O�J���V���c�A�^�I���ށA�������Z�b�g�ABOX�e�B�b�V���A�h�����N�{�g��&�R�b�v�Ȃǂ�
���p�i�ꎮ�ł����B
�Ō�t����A3/31����3���Ԃ̐�H�������n����A�\���܂ł���܂����B
�A���A���A�����A�R�[�q�[�Ȃǂ̃A���R�[���ȊO�̈��ݕ���OK�Ƃ̂��ƁB
|
|
| 3��31������H�̓\���@(2023.03.31_15:29) |
�@�ȍ~�A�S���Ō�t����ɂ�����I�Ȍ����A��������A�_�H�t�̕�[���s���܂����B
�ދ��疜�ł��B
TV�����̂��߁A�v���y�C�h�J�[�h��1,000�~/�� ���ăq�}�ׂ����邵������܂���ł����B
�@3/29�̒��̔r�ւŁA�����͂���ɍ����ւ��Ȃ��Ǝv���Ȃ���A���̗[�H�͉���������? ��
�L�������ǂ��Ă݂܂������A�v��������߂͂���܂���B
���𗬂����ƕ֊��������ƁA�r�b�N���V!!
��ʂ̐^���ԂȑN���Ő��܂��Ă�������ł��B
���ւł����B
�@����Ȃ��Ƃ́A���܂�ď��߂Ă̌o���ł��B
����܂ł����̒ɂ݂����a���Ȃ����Ǐ����̂Ńr�b�N�����܂����B
�Ђ���Ƃ�����݊����咰���ł����ǂ����̂��Ƒ�ϐS�z�ɂȂ�܂����B
�@�O�ׁ̈A���N��f���Ă��������f�̃f�[�^�[�ׂĂ݂܂����B
�ߋ�3�N��(20/21/22�N)�̑咰�K�������ňُ�Ȃ��A����(20/22�N)�̈݃J����������
�m���Ɉُ햳���ł����B
�@�䂪�ƌn���`���I�ɃK���̉ƌn�ł�����܂���B
�Ƃɂ����S�z�Ȃ̂ŗ[���A�߂��̂��������ł�����Ȉ��K��܂����B
��N���A�o�ߊώ@���ł����������l�̌��������˂āB
�@���������ɐH���Ö@���َ̐҂̌����f�[�^�[���A���ւ̏Ȃǂ�����B
�Ƃ肠�������t���������܂��傤�Ƃ̂��Ƃō̌�����A2����ɍĐf��ʍ�����܂����B
���i�A���ւɑ���R�����g�͂���܂���ł����B
�@���̓��A��������ォ��H���ɂ��ẴR�����g�����������̂ŁA���i�ʂ�[�H���D����
�A���R�[�������݂܂����B
�@3/30�A���̔r�ւ��ώ@�����Ƃ���A����Ă����Ƃ���Ăу��C�����b�h�̌��ւ������̂ł��B
��ςȎ��Ԃł��B
���l�ɋ��鏗�[�ɓ`�����Ƃ���A���Ȃł͂Ȃ���������Ȃ��ݒ����Ȃ������́A�����Ƒ傫��
�a�@�Őf�Ă��炢�Ȃ����ƁB
�@�Ƃ������ƂŁA���̒n��̕a�@�ł���W�C��ÃZ���^�[�ɑ��k���Ă݂܂����B
�Љ��̂Ȃ��O�����f�ł����f���ȊO�ɑI��f�Ô�(7,700�~)���|���邪��f�ł���Ƃ�
���Ƃł����B
�����ɂł��A���ւ��������������Ȃ���f���ꂽ��ǂ��ł����ƁB
�@����ȏł�����A�����Ď��Ԃ̐��ڂ����Ă���킯�ɂ͂����܂���B
��������Ԃɏ�������ȂŐ��������̎�f�����f�B
�[�������ւł����̂ŁA��8���܂łɗ[�H���ς܂��A�ȍ~�͐���H�Ƃ��܂����B
| �����̕x�m�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ 1118-2023.03.22�@ |
�@�����̂��V�C�͑S���I��   �ł��B �ł��B
�@�g�����Ȃ�t�߂��Ă��܂����ˁB
�e�n������̊J�Ԃ̕ւ��������鍠�ɂȂ�܂����B
3�����{���ɂ͖��J�̌����ɂȂ�ł��傤�l!
�@AIOI���b�g�N���u�̃I�[�i�[��K.T-san���獡���̕x�m�R�̋�B�ʐ^���͂��܂����B
�L�����ʏo���̂��߉H�c���������@�ォ��B�����Ƃ̂��Ƃł��B
���V�C���ǂ���������ł��傤���A���Ⴕ���x�m�R�̒�����ӂ��������茩���܂��B
�f���炵���x�m�R�̉f���������ɃA�b�v���܂����̂ŁA�F����������ɂȂ��ĉ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N����Ƒ��ʂł��ɂȂ�܂�
�����̕x�m�R(2023.03.22_15:00�B�e)
(Photos by K.Tada-san) |
|
�@�����āA�������ɐÉ������쒬����B��ꂽ�����̕x�m�R�����Љ�܂��傤�B
���쒬�ݏZ�̊w������̋��F�ł���A���b�g/���]�Ԓ��Ԃł���M.Tamura-san���u���O
����ʐM�́u�����̕x�m�R�v����̓]�ڎʐ^�ł��B
�ނ̂����ӂŃA�b�v�����Ă��������܂����B
�@������6����7�����ɂɎB��ꂽ�x�m�R�ł����A1���Ԍ�ɂ͕��͋C���ω����Ă��܂��l!
�����̒��ɕx�m�R�̗Y�p���܂邲�ƁA��������ƌ�����f���炵���ʐ^�ł��B
|
|
|
�����̕x�m�R(2023.03.22_05:56�B�e)
(Photo by M.T-san) |
�����̕x�m�R(2023.03.22_06:55�B�e)
(Photo by M.T-san) |
�@�����Ă��̓��A��5��WBC(���[���h�E�x�[�X�z�[���E�N���b�V�b�N)�̌����킪�ă}�C�A�~��
���[���f�|�E�p�[�N�ŕč���\�ƍs���܂����B
�َ҂���7������TV�ɂ�����t���Ŋϐ�A�n���n���h�L�h�L�̖�3���Ԃł������A��Japan��
�č���3��1�Ŕj��A3�x�ڂ̗D���𐬂����������Ƃ��NjL���Ă����܂��B
|
|
WBC�ŗD�������ߕ��������Ċ�ԓ��{��\�̑I�肽��
[�o�T]�����V��2023.03.23���� |
�@AIOI���b�g�N���u�̍��N�ŏ��̃��b�g�Z�[�����O�ɎQ�����܂����B
�ɓ��w�̃R���r�j�ň����B���Ĉɓ��T�����C�Y�}���[�i�[�ցB
�撅���Ă����N���[�����o�[��Ktym-san���o�`�̏������ł����B
�@1�N�U��Ɍ���}���[�i�[�̌i�F�ł��B
�������܂�1�N���߂��AAIOI���ł̃Z�[�����O���牓�������Ă�������ł��B
|
|
| ���̃T�����C�Y�}���[�i�[�@(2023.03.12_10:32) |
�@�܂��ł������₩�ȊC�ł��B
�N���[�����o�[�̓L���v�e��K.T����AKtym-san�AM.Miyake-san�Ɛَ҂�4���ł��B
���̃����o�[�ł̃Z�[�����O�͏��߂Ăł��B
���ϔN��炵�āA�V�l�Ət�̊C�Ƃ��������ł��傤���B
�@�����̃Z�[�����O�͏��������ł��B
�����ɏ㗤����AIOI����p�B�̊C�N�H���E����Œ��H��\�肵�Ă��܂��B
�@11:00�߂��ɏo�`�B
�X�N�����[�̃f�B�[���G���W���쓮���獂���\�o�b�e���[�쓮�ɕς���Ă��珉�߂Ă̏�D
�̌��ł��B
Li-ion�o�b�e���[�ł̃��[�^�[�쓮�ł�����r�K�X�������A���ɐÂ��ȑ��s�ł��l!
�@�@�����甿���ɐ�ւ��đ��s���܂����A�x�X������ԂɊׂ�܂��B
����ł����������݁A1�`2�m�b�g�ŏt�̊C���̂�肭���Ɛi�݂܂����B
|
|
|
| �����Ɍ�����������AIOI���@(2023.03.12_11:34) |
�r�[���u���[�N���̖ʁX |
�@�����߂��ŋ@���ɐ�ւ��A12:30�A�����t�C�b�V�����[�i�ɓ��`�A�V���ɌW���B
�t�C�b�V�����[�i���Â��ł����B
|
|
| �����t�C�b�V�����[�i��AIOI���@(2023.03.12_12:40) |
|
|
|
| �����t�C�b�V�����[�i�ŊF����ƋL�O�ʐ^�@(2023.03.12_12:39) |
�@�V���̗��d�{�݂Ńo�b�e���[�[�d�̏��������āA�����`�߂��̐H���X�ցB
�����ł������^�ǂ��C�N�H���E����ɓ���܂����B
�@���ړ��Ắu�����������^�Ă��v�Œ��H�B
�����ߊC�Ŋl�ꂽ�V�N�ȃC�J�����ƔZ���Ȋ̂̃��^�Ă��͍ō��ɔ�������!!!
|
|
| ����̂����������^�Ă��@(2023.03.03_13:05) |
�@AIOI���ɖ߂��āA���炭���C���őD���ł��B
AIOI���V�F�t����Ktym-san���p�ӂ��Ă��ꂽ���E�܂݂ŁB
|
|
|
| ���C���őD���@(2023.03.12_14:14) |
|
|
AIOI���̃��C���Z�[��
(2023.03.03_15:46) |
�@14:30�A�����t�C�b�V�����[�i�𗣊݂��ĕ��H�ɏA���܂����B
���H�Ƒł��ĕς���ėǂ����ł��B
�قڈɓ��}���[�i�܂ł̑S�s����3�`8�m�b�g�̃X�s�[�h�Ŕ����B
�u�ԑ��x�ňꎞ�A9�m�b�g���L�^���܂����B
|
|
|
�ǂ����L���v�e��K.T-san
(2023.03.12_15:00) |
�������s����AIOI��
(2023.03.12_15:31)) |
�@16:20�A�T�����C�Y�}���[�i�[�ɋA�`�B
��n�������ă}���[�i�𗣂�A17:22�ɓ����ɓ����M�C�s���ɏ��A�H�ɂ��܂����B
�@�v���Ԃ��AIOI���ł̊y�������b�g�Z�[�����O�ł����B
�����ɏ㗤���Ĕ��������C�J�������^�Ă������\�ł��܂����B
���ꂩ����ł��邾��AIOI���ł̃��b�g���C�t���y���݂����Ǝv���Ă��܂��B
�F����A�����͂��肪�Ƃ������܂����B
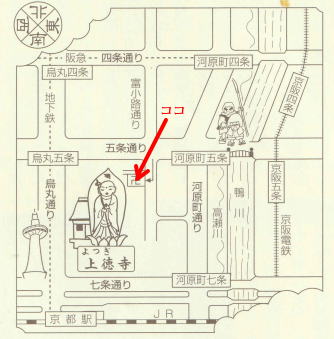 |
| �㓿���̃��P�[�V���� |
�@�����₩��㓿���܂Ń^�N�V�[��10������
�����܂����B
�㓿���͌�ʂ�ƕx���H�ʂ�̌����_��
���܂��Ē����E��ɂ���܂��B
�@�㓿���̎R��ł��B
|
|
| �㓿���R��@(2023.03.03_14:56) |
�@�R��ɂ͏㓿���̃K�C�h������A��ʂ肨���̗R���ɓ���ċ����ցB
�ܘ_�A���߂Ĕq�ς��邨���ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N���đ��ʂł���������
|
|
| �㓿���̗��j�̊T������������Ŕ@(2023.03.03_14:56) |
�@�O�ς��炵�āA������܂肵�������̂悤�ł��B
���ʂɖ{��������܂��B
|
|
| �㓿�� �{���@(2023.03.03_15:22) |
�@�����ɓ����t�Ŕq�ϗ�800�~��[�ߏ㓿����
���[�t���b�g��Ⴂ�A�K�C�h����Ɉē�����Ė{���ցB
�@���̔q�ώ҂Ƌ��ɃK�C�h����̐�����q���B
�����̗R��/���jetc.�ł��B
�E1603�N(�c��8�N)����ƍN�̌���������y�@���@
�E�R���́u�����R(��������)�v
�E�ƍN�̑��� ���������J��
�E�{����1753�N(���3�N)�̌����ŁA���X�͋��s��
�@�i�ϓ��ɂ������u�c�t���v���ڒz�������́B
�E�{���͈���ɔ@������(���q����A�` ���c��A����97.3cm�A�����̊��A���Îs���
�@�ڍ������{���������������́A���ݏd���̎w�蓚�\��)
�E�u�q�����E���Y�v�����v�ŗL��
���A���̂����ł́A���̓~�̗� ���ʌ��J�G���A�S�ĂŎʐ^�B�e���ł���Ƃ̂��Ƃł��B
|
|
| �{���Ɋ|�������G�z�̎R���u�����R�v�@(2023.03.03_15:13) |
�@�{���̓��w�ł��B
���c��Ɠ`���{���̈���ɔ@�������͓������������قł̌��N�f�f�ŏo�����̂���
�q�ςł��Ȃ������̂��c�O�ł����B
|
|
|
| �{�����w�̐{��d�@(2023.03.03_15:11) |
�{���E����ɔ@�������̐����p�l�� |
�@�O�w�̕��Ԃɂ��鎛��̊|�����̐����ł��B
������u�߉ޟ��ϐ}�v�A�u����ƍN�ё��v�A�u�����̋Ǐё��v�A�u����G���ё��v�ł��B
�ǂ̊|��������ҕs�ڂƂ̂��Ƃł����B
|
|
| ����̊|�����@(2023.03.03_15:11) |
�@�ё��̊g��ʐ^�ł��B
�ǂ̊|�����������ɂ݂����肭����ł��܂����B
|
|
|
|
| �����̋Ǐё� |
����ƍN�ё� |
����G���ё� |
�@�����ǂ͕v�Ǝ��ɕʂꂽ��A�ƍN�̑����ƂȂ����B
�ƍN����ł������ꂽ�����ŁA�n�p�A���p�ɗD��A���ւ����s�����Ƃ����˒m�ɕx�����ŁA
�ƍN�S������o�Ƃ����A���{��㏫�R�G�����x�����Ƃ̂��Ƃł��B
�G���͉ƍN�Ɛ����̋ǂƂ̊Ԃɐ��܂ꂽ�q�ł����A�����ǂɂ��{�炳�ꂽ�Ƃ��B
�@�����ċq�a��q�ρB
�ʂ̃K�C�h���������Ă��������܂����B
|
|
|
| �㓿�� �q�a�@(2023.03.03_15:13_) |
�q�a���ɂ��鏑�@�@(2023.03.03_15:14_) |
�@�q�a�́A��������ɐ���@�ɂ��������ƏZ����ڒz���ꂽ�Ɠ`������]�ˎ�������
���@����̌����B
���@�ɂ́A��O����u�g�t�̊ԁv�A�u���̊ԁv��2����������܂��B
���̊Ԃɂ͍]�ˎ���̊G�t�A�~�R������̊|�������B
|
|
| �q�a���̊Ԃ̊|����(�~�R ���� ��) |
�@���@�̑O�ɂ͎͌R���̒뉀������܂����B
���a�ɍ�낳�ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B
|
|
| ���@�O�͎̌R���뉀�@(2023.03.0315:14) |
�@���H�ɏ]�������Ēn�����ցB
|
|
| �㓿�� �n�����@(2023.03.03_15:20) |
�@�����̒��ɓ���ƁA���ʂɐ��p�n��(�n����F����)�����u���ꂽ�{��d���B
���̒n������A2m���̑傫�Ȑɒ����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B
�{��d�����ʂ̔�������q�ς��܂����B
���̂��n�������q�߂A�q�����E���Y�̂����v������Ƃ̂��ƂŁA���́u�������v�Ƃ���
�e���܂�Ă���Ƃ��B
|
|
|
| �n�����̐{��d�@(2023.03.03_15:16) |
���ʂ��璭�߂��̒n����F�����@(2023.03.03_15:17) |
�@�Ō�͈�ʌ��J�G���A�ɂ���u�����ǂ̕�v���������܂����B
�����ǂ̂���́A�����s�]����́u�_���@�v�A���s������́u�����������v�ɂ�����悤�ł��B
|
|
| �㓿�� �����ǂ̂���@(2023.03.03_15:18) |
�@��25�����̑����̏㓿���̔q�ςł����B
����ŁA�{���́u���̓~�̗��v�L�����y�[������3���̔q�ς��I���B
�s�o�X�ŋ��s�w�������܂����B
�@�m���@�̎��͐������ł��B
�^�N�V�[�ō~�肽�̂��������肫�����Ƃ���ł��B
|
| 2023�E���̓~�̗� �s���}�b�v�s�� |
�@��������y�Y�X������A�˂���̐����������������ցB
�m���@�Ƃ͂����ĕς���Ă����̂悤�Ɋό��q�ł������Ԃ��Ă��܂����B
|
|
| �ό��q�ł������Ԃ�������̂��y�Y�ʂ�@(2023.03.03_13:21) |
�@�Ⴂ�J�b�v����O���l�ό��q�����������ł��ˁB
���s�ό��ł̓g�����g�Ȃ�ł��傤���A�����^�������p�̃J�b�v����C���o�E���h���q�̎p��
�ڂɕt���܂����B
�@�����肫��Ɛ��ʂɐm����A����A�O�d������ɉf���Č����܂��B
�ǂ���A�C���o�E���h�D�݂̎�h��ł��B
|
|
| �������̐m����(��)�A����A�O�d����]�ށ@(2023.03.03_13:24) |
�@�Βi�����m�����������ƁA����̍���ɏ��O������A�X�ɏ��ƎO�d�����B
|
|
|
�m���傩�琼��ƎO�d����]��
(2023.03.03_13:26) |
���O���狞�s�s����]��
(2023.03.03_13:28) |
�@�O�d���̐�̌o�������܂��āA���A�@�˂̈ē��W���ɏ]���Ȃ��炩�ȍ������Ɛ��ʂ�
���A�@���B
����̃L�����y�[���œ��ʌ��J����Ă���̂��A�������A�@�̒뉀�u���̒�v�ł��B
|
|
| ���A�@ (2023.03.03_13:35) |
�@��t�Ŕq�ϗ�600�~�����ߏ��@�ցB
�q�ϋq�����Ƌ��ɃL�����y�[���E�X�^�b�t�̐������Ɛ��A�@�̘b�Ɏ����X���܂����B
�@���H�R�̒����ɍL���鐴�����́A��a���E�������̑m�E���S(��ɉ����Ɖ���)�ɂ��778�N
(��T9�N)�ɊJ�n���ꂽ�Ɠ`���B
�n���ȗ��A10�x�����Ђɂ������̂��тɓ������Ď��������A�Ă��M�ɂ�艽�x���Č�
���ꂽ�B
���݂̉����͂قƂ�ǂ�1633�N�ɍČ����ꂽ���̂ł��B
�@�J�n�ȗ��A�ޗǕ������@���@���@�|�Ƃ��A�����E�ߐ��ɂ����Ă͖@���@��{�R�A������(�ޗ�)
�̖����ł����B�@
���������k�@���@�̖{�R�Ƃ��ēƗ������̂�1965�N�����������ł��B
�u�w�k�x�@���@�v�Ƃ������̂ɂ́A��s�ƌĂꂽ�ޗǂɑ��āA�k�Ɉʒu���鋞�s�Ŗ@�����f����
�Ƃ����Ӗ������߂��Ă���Ƃ̂��Ƃł��B
�@���������A�@�ɂ��āB
���A�@�͐������̓������@�ŁA���m�̗��̕��ɂ������������������舢��l�ɂ����
�n�����ꂽ�B�@���̌�A���x�ƂȂ��ЂɌ������A���݂̌�����1639�N(���i16�N)�ɓ���
�ƌ��̖��Ō㐅���V�c�̍@�ł�����������@�a�q�������������̂������ł��B
�@�����̒뉀�͐ጎ�Ԃ̎O�뉑�̈�u���̒�v�Ƃ��Ēm����،i���r���V���뉀�ł��B
�H���Ȍ�������ɏƂ炳�ꂽ��̔��������y���ނ悤�ɍ��ꂽ���낾�����ł��B
���䎛�R���،i�ɂ����뉀�́A�������������������������A���l�E���x���B����C��
���Ƃ��A�]�ˊ��̔o�l�E���i�哿�̍�Ƃ��`������]�ˎ��㏉�����\���閼��B
�@2022�N�ɖk��V���{�Ɂu�Ԃ̒�v���ċ�����A���k�̖������́u��̒�v�Ƌ��ɋ��s�ɂ���
�u�ጎ�Ԃ̎O�뉑�v�ƌĂ�Ă���B
��������A�u���A�@(���A�V)�v�Ɩ��̕t���O�̂����ɏ��i�哿����낵���Ƃ����B
�@���̐��A�@�ł͓���������ʐ^�B�e���֎~����Ă��āA�������ł��Ȃ��̂��c�O�ł��B
����́A�f�ڂ̎ʐ^�͐������̃z�[���y�[�W������p(�R�s�y)�����Ă��������܂����B
�@�@�@���A�@�뉀���ʌ��J | �s�� | ���H�R ������ (kiyomizudera.or.jp)
�@����̐����Ɨ��}�́A�p���t���b�g�u�����@���������A�@�̒뉀�v�������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N���đ��ʂł���������
|
|
| �u�����@���������A�@�̒뉀�v�̐����Ɨ��}�@(2023.03.03) |
�@���Ə�l�E�M�C��l�������J���Ă��镔���ŃX�^�b�t����̐����ł��B
�@�����ɋΉ��m�Ƃ��Ēm��ꂽ���Ə�l�Ƃ��̎���M�C��l���Z�E���߂����Ƃł��m���A
����������߉q��꤂炪���A�@�ɏW�܂��Ė��k�����Ƃ��m���Ă��܂��B
1848�N(����5�N)����n�܂��������卖�ŁA�M�C��l�͓�������]�˂ō��������܂����B
����A���Ə�l�͐����Ƌ��ɎF���˂ɓ���܂����B�@�������A�˂ł͖��҂Ƃ��ē�l�������
�֒Ǖ��A�O�r��ߊς�����l�͋э]�p�ɓ������A���Ə�l�͖��𗎂Ƃ��A�����͈ꖽ�����
���߁A���̌�A�F���ɖ߂��ꑸ�c���ւƂ��̗͂𒍂����@�Ƃ̂��Ƃł��B
�@30���������w������A�q�ϗ�400�~�Ő������{�̂��������邱�Ƃɂ��܂����B
������́A���A�@�Ƃ������đ傢�ɍ��G���Ă��܂����B
�@����(�d��)��ʂ�߂��Ė{���̕��������܂��B
�吳�ʂ̌����ɂ́u����t�v�Ɗ��|���ꂽ�G�z���B
�Ӗ��ׂĂ݂�ƁA�u�~�������߁A�����𐿂��A�����J���̂ɐg���͊W�Ȃ��B���̒��̐l
���ĂɊJ���ꂽ��ł���A�J���ꂽ�C�s�̏ꏊ�ł���v�Ƃ̂��Ƃł��B
|
|
| ������ ����@(2023.03.03_14:13) |
�@�@�L���`���ɉ��i�ނƍ���E�{�����䂪�����܂��B
�L���ł̓����^�������p�̃J�b�v�������������Ŏʐ^���B��p���B
|
|
|
| �{���Ɍ������L���ɂā@(2023.03.03_14:11) |
�����@�{������̐����@(2023.03.03_14:16) |
�@�{���ɓ���ƒ����ɁA�����₩�ŗD�����\��������单�l���}���Ă���܂��B
�o���单�V��(��������)�ƌ����A�o���E�����ɐ��̂����v������Ƃ��B
|
|
| �o���单�V���@(2023.03.03_14:18) |
�@�����Ő����̕���Ƃ��Ēm���鐴�����{���ɂ��āB
�@�@�@���݂̌����́A����ƌ���i�ɂ��1633�N(���i10�N)�ɍČ����ꂽ�B
�@�@�傫���͐���36m���A���ʖ�30m�A����28m�B
�@�@�@�����͊O�w�Ɠ��w�A���X�w�̎O�ɕ�����A�O�w�̊O���ɘL�����z�u����Ă���B
�@�@���X�w�ɂ͎O��̐~�q���u����A�����̐~�q�ɂ͖{���̐��ω����A���̗����̐~�q
�@�@�ɂ͘e���Ƃ��Ă̔�����V�����A�n����F���������u����A��������镧�B
�@�@�@�{���~�q�̍��E�ɂ͐��ω����ő��ł����\�����O�������u����A���X�w���E�[
�@�@�ɂ͕��_�E���_�������u����Ă���B
�@�@�@�����̕���́A�{���̊ϐ�����F�Ɍ|�\���[����ꏊ�ł��B
�@�@�Â������y�A�\�E�����A�̕���A���o�Ȃǂ̌|�\����[����Ă����B
�@�@���݂ł������[���s���Ă���B
�@�@�@�{�����璣��o�����u����v�̍����͖�13m�ŁA�����4�K���Ẵr���ɑ�������B
�@�@���H�R�̋}�s�ȊR�Ɍ��z����Ă��܂��B
�@�@����́u�����v(�����Â���E���䑢�Ƃ�����)�ƌĂ����{�×��̓`���H�@�ŁA�i�q���
�@�@�g�܂ꂽ�؍ޓ��m���x���������z������ȊR�Ȃǂł��ϐk���̍����\��������グ��
�@�@���Ƃ��\�ɂ��Ă��܂��B
�@�@�@������x���Ă���̂́A�����Ɍ��Ă�ꂽ18�{���̒��ł��B
�@�@����400�N�]�̟O���g���A�傫�����̂Œ�����12���[�g���A���͖�2���[�g���̒������R��
�@�@����ł��܂��B
�@�@���̏c���ɂ͉��{���̊т��ʂ���Ă��܂��B
�@�@�؍ޓ��m�������݂ɐڍ����邱�̍\���́u�p����v�ƌĂ�A�B��1�{���g�p���Ă��܂���B
�@
�@�@�@���݂̕����1633�N�ɍČ����ꂽ���̂ł��B���j��A���x���������ЊQ�ɂ��ς��A����
�@�@���X�����̎Q�w�҂œ��키������x�������Ă��܂��B
�@�@�@���{�ɂ́u�����̕��䂩���э~���v�Ƃ�����������܂��B
�@�@�藧�����f�R�ɒ���o���Ă��鐴�����{���̕��䂩���э~���قǂ̏d��Ȍ��ӂ�
�@�@�����ɂ̂��ނ��Ƃ�\�������t�ł��B
�@�@�@���A����̏ꏊ�ɓo�ꂷ�邱�Ƃ��u�w����ށv�Ƃ����\�������܂��B�@�������̞w����
�@�@�����̌ꌹ�ɂȂ����Ƃ��B
�@[�o�T]���j | ���H�R ������ (kiyomizudera.or.jp)
|
�@���䂩�璭�߂��i�F������B
���ʂ̎R�̒��Ɏ�F���N�₩�ȎO�d���������܂��B
Net�Œ��ׂĂ݂�ƁA�q�����ƌ����������̓����̑Y���̎O�d��(���̎ʐ^�E����)�Ƃ̂���
�ł����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �摜���N���b�N���đ��ʂł���������
|
|
|
|
�ቺ�́u���H�̑�v�߂�
(2023.03.03_14:16) |
��F�̎q������]��
(2023.03.03_14:16) |
����ɓ����ʂ�]��
(2023.03.03_14:16) |
�@��������H�ɏ]���Đi�ނƁA��F���N�₩�Ȉ���ɓ�(�d��)���B
�]�ˎ��㏉����1631�N�̍Č��B ���ꉮ����A�w�畘�̌��z�l���B
�����d�グ�̖{���E����ɔ@�����������u����Ă��܂��B
|
|
|
| ����ɓ��@(2023.03.03_14:21) |
����ɓ����̈���ɔ@�������@(2023.03.03_14:22) |
�@���O�w�����̍���̒��Ɂu���z�Z����ɔ@���O������v����(�E�ʐ^�̍��[)���|����
���܂��B
[��]��(���)�Ƃ́A����G���������蒤�������肵�āA����ǔȂǂɍ��E�����Ċ|���ď���
�@�@�@�Ƃ���ג����̂��Ƃł��B
����́A�@�R��l�������Ŗ�ɂ̖{��O���̋���������A�킪���ŏ��̏�s�O�����s��ꂽ����
�ɂ���Ă��邻���ł��B
���Ȃ݂ɗ��z�Z����ɂ́A������̐^�@���E�i�ϓ��A���R��̂����������E���ˉ@�E���{���A
������̐��莛�ł��B
�@����ɓ���ׂ̉��̉@���璭�߂��{��/����̒��߂��������B
|
|
|
| �ό��q�œ��키�����̕���@(23.03.03_14:23) |
�{���̑S�̂�]�ށ@(23.03.03_14:25) |
|
|
|
| �������{��&�d���Ƌ��s�s����]�ށ@(2023.03.03_14:27) |
�@�⓹������A�����̕���������璭�߂Ă݂܂����B
���₠�A����̊ό��q������Ȃɏ����������܂��B
����13m������܂�����l�I
|
|
| �����璭�߂��u�����̕���v�@(2023.03.03_14:31) |
�@�m����O���琴����ɏo�āA�q�҂����Ă����^�N�V�[�ɏ��A�{���Ō�̖K��n�E�㓿����
�������܂����B
�^�N�V�[�̉^�]�肳��ɂ��ƁA�O���l�ό��q�͒����l�͏��Ȃ��A���̑����͑�p�⍁�`�����
�ό��q�������ł��B
�R���i�Ђ̉e���ŊO���l�̔䗦�����ς����悤�ł��B
���� Diary-2.archive.2023.03 / No.116-2023.03.03 / Diary-2.archive.2023.03 / No.116-2023.03.03 /
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���̓~�̗�(3/3)�`�����R �㓿���`�v
�@�W�p���O��y��(1����)�ɂ��ƁA�u���̓~�̗��v�L�����y�[�����J�Ò��Ƃ̂��Ƃł��B
���̃L�����y�[���A���a42�N(1967�N)1���ɊJ�Â���Ă���57��ڂ��}���邻���ł��B
�@���N�̃e�[�}�́A��̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v���f�ɂ��Ȃu�ƍN�ɏo����̗��v��A�u�e�a
���l��a��850�N�v�A�u�O�@��t��a��1250�N�v�ł��B
����ƍN�⓯��������퍑�����䂩��̎��@�ŁA�������p�₻�̕����ɃX�|�b�g������
�����̔���J�����������ʌ��J����Ă��邻���ł��B
�@��57��u���̓~�̗��v�L�����y�[���̌����T�C�g�͂�����ł��B
�@��57�� ���̓~�̗��i2023�N1���`3���J�Áj�b�y���s�s�����z���s�ό�Navi (kyoto.travel)
�@�ƌ������ƂŁA�����g�����Ȃ������Ƃ�����A���w�ɏo�����܂����B
�����G���A�ɂ���m���@�����������㓿���̏���3����K�˂܂����B
|
|
2023�N�u���̓~�̗��v�L�����y�[��
�p���t���b�g�̕\�� |
�@�悸�ŏ��́A�m���@�ł��B
JR�R�ȉw�Œn���S�������ɏ抷���A�O�ڂ̓��R�w
�ʼn��ԁA�~�{���ɏo�ēk��10��(��600m)�B
�@�~�{���ɏo��Ɩk���Ɏ�F�̕����_�{�̒���������
�܂��B
���̔��Ε����ɕ����Ɛ@�@�ׂ̗肪�m���@�ł����B
�@�@�@�@�@ �摜���N���b�N����Ƒ��ʂł��ɂȂ�܂�
|
|
�~�{���ɉf���镽���_�{�E����
(2023.03.03_11:48) |
�@�m���@�͖@�R��l���J�R������y�@���{�R�̎��@�B
����ƍN�䂩��̎��������Ƃ͒m��܂���ł����B
�@�ƍN�ƒm���@�̊W�͎��̂悤�ł��B
�ƍN�̏@�|�͏�y�@�B�@1602�N(�c��7)8���A�ƍN�̐���E�����̕������̕�����Ŗv�������A�ƍN�͂��̑��V��m���@�ōs���܂����B
���̂���̈Ӗ����������̂��A��1603�N�ɂ́A�m���@��703�Η]��̎��̂���i���A������
�g���H�����s�������肩�A1607�N�ɂ́A��z���V�c�̍c�q�E���{(�Ǐ��@�e��)���Ղ�
�����A�m���@���Վ��@�ɂ��Ă��܂��B
�@�m���@�̎O��O�ɒ������̂������O�ł����B
����E�O��(�O��E��)�͂����Ă��ł������ł���!
��������������A�Q�q�q�̏����ɋL�O�ʐ^���B���Ă��炢�܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N����Ƒ��ʂł��ɂȂ�܂�
|
|
|
| �m���@�O��@(2023.03.03_11:54) |
�O��O�ŋL�O�ʐ^�@(2023.03.03_12:00) |
�@1621�N(���a7)�A����2�㏫�R�G���̖��Ō����B
����24m�A����50m�A��������7�����ł��̍\���E�K�͂ł͉䂪���ő勉�̖ؑ���ł��B
�u�ؒ��R�v�̝G�z�̑傫���͏�2�����������ł��B
�@�O���������傫�ȐΒi���G�b�`���I�b�`�����ƁA�傫�ȉ����̂��鋫���ɏo�܂����B
�@�R��l����e���J��u��e���v�ł��B
1639(���i16)�N�ɓ���3�㏫�R�ƌ��ɂ�茚�Ă�ꂽ�Ԍ�45m�A���s��35m�A��3m�̑s���
�����ł��B
|
|
|
| ��e���O�̍L�������@(2023.03.03_12:03) |
��e����]�ށ@(2023.03.03_12:03) |
�@��e���ɏオ�菇�H�ɏ]���A���̘L���`���ɗ��ɉ���W��ɃC�x���g�̔q�ώ�t������܂����B
�q�ϗ�800�~��[�߂ē����ցB
��������ʐ^�B�e�͋֎~����Ă��܂��B
����́A�ʐ^�����j�ƌ��ǂ���b��y�@���{�R �m���@ (chion-in.or.jp)�����p������
���������܂����B
�@�����Ē����̂Ƃ���ɁA�@�R��l�s��G�}(����Ƃ��Ắw�@�R��l�G�`�x�Ƃ��ēo�^�����
����)�̃��v���J���W������Ă��܂����B
�m���@�ɓ`���@�R��l�̓`�L�G���ŁA��l�̖v��100�N��ɍ��ꂽ���̂�48������Ȃ�
�����ł��B
�@����֓���܂��B
1641�N�ɉƌ������������召�̕���́A���R���Q�q���ꂽ�ۂ̋����Ƃ��Ďg�p����܂����B
�@�悸�͑����ł��B
�Ԍ���36m�A���s��25m�̍L���ł��B
���@����̌`��������A54��̕��ԁu�߂̊ԁv�𒆐S�Ɏ��h�̋��ɉ�ɏ����ł��܂��B
�@����䢒߂̊ԣ�̉��G�w�Q�ߐ}�x�ł��B
���T�H�̒�E���M�ɂ��A16�ʂ̋�����9�H�̒߂��`����Ă��܂��B
�@�u�߂̊ԁv�̐��ׂɂ���̂��u���̊ԁv�A�L����27��B
�k�E���E����14�ʂ̉��ɂ́A�������Œ߂Ƌ��ɏ�����̂ɕ`����Ă��܂��B
���̉��G�̍�҂���쏮�M�Ƃ����B
�@���R���y������ۂɎg���u��i�̊ԁv�A���@����̌`���ł��B
�@����̘L���łȂ����������ցB
�����X�^�b�t�ɂ��ƁA��������̘L���́A��e����
�W�������䁨�q����Ɏ���S��550m�̘L���ŁA
��������̖����Ɏ��������o�āA����ɂ͋Ȏ҂�
���邽�߂������Ƃ��B
�@�q����͑����̖��̃X�y�[�X�A6������Ȃ�B
����䂪�p�u���b�N�X�y�[�X�Ȃ̂ɑ��A�q����̓v���C
�x�[�g�X�y�[�X�B
�����畧�Ԃ��Ȃ����A��lj�����n��ȂǗ���������
���̂���ł��B
�@�u�ᒆ�R���̊ԁv�ɂ́A��쏮�M�M�́u�ᒆ�R���}�v�̉��G�B�@���̕ǂɂ́u�ؒ��R�v�Ə����ꂽ
�|�������������Ă��܂����B
�O��̝G�z�ɂ���u�ؒ��R�v�Ɠ����傫���������ł��B
�@�����ĕ���뉀������뉀���q����뉀���������̏��H�Ō��w���܂����B
�@����뉀�͍]�ˎ��㏉���ɏ��x���B�Ɖ��̂���m�ʕ��ɂ���č�낳�ꂽ�Ɠ`������
���܂��B
���R�R�[�̍��፷�����A�Z�\�`�̒r�𒆐S�ɂ����r���V���뉀�ŁA����̉ؗ�Ȍ��z
�ƂƂ��ɁA����ӂ����������i�������o���Ă��܂��B
�@�����뉀�ł��B
|
|
| �����뉀�@(2023.03.03_12:41) |
|
|
|
�����뉀�@�u�ƌ������A���̏��v(����)��]��
(2023.03.03_12:43) |
�����뉀�@(2023.03.03_12:47) |
�@�q����̒뉀�ł��B
�ʖ��u��\�ܕ�F�̒�v�ƌĂсA�m���@�̍���u����ɔ@����\�ܕ�F���}�}�v����ɂ���
���̂ŁA�ՏI�̎��ɁA�O�����̂���Έ���ɔ@����25���̕�F���Ɋy��y�}���ĉ�����
�l��ƐA�����݂ŕ\���������̂������ł��B
��ɔz�u����Ă���͈���ɔ@���Ɠ�\�ܕ�F���A�A�����݂͗��}�_��\���Ă���B
|
|
| �q����뉀(��\�ܕ�F�̒�)��]�ށ@(2023.03.03_12:43) |
�@�q����̒�̉��ɐi�ނƏ��K�͂ȕ����A�u�������v���B
1956(���a31)�N�ɏĎ���A��y�J�C800�N�̋L�O���ƂƂ��āA1974�N�ɍČ��B
�����ɂ͒m���@�̑��c�Ɋւ��������O��(�ƍN�E�G���E�ƌ�)�̏ё���ƈʔv�����u�����
����B
|
|
|
| �������E�y�� (2023.03.03_12:44) |
��������]�ށ@(2023.03.03_12:46) |
�@��1���Ԃقǂ̌��w�ł����B
����܂Œm���@�̎O��͉����Ă܂����A�����̓��F�ɓ��茩�w�����̂͏��߂Ăł����B
�������ɁA��y�@���{�R�̎��@�ł��B
�������̂������������܂����B
�������炳�قlj����Ȃ��̂ŁA���Ԃ̓s��������^�N�V�[�Ŏ��̐������Ɍ������܂����B
���� Diary-2.archive.2023.03 / No.115-2023.03.03 / Diary-2.archive.2023.03 / No.115-2023.03.03 /
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���̓~�̗�(2/3)�`�������`�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ TOP�y�[�W�֖߂� TOP�y�[�W�֖߂�
|
|